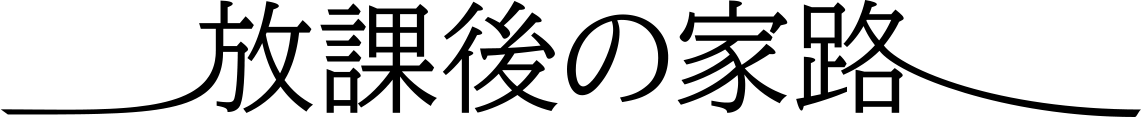そういえば書いていなかった。2023年10月に、国書刊行会から発刊された『吉田健一に就て』という本に、本名の堀田隆大の名義で執筆参加していました。本に賞味期限は無いし、ネット通販でも販売されているので、気になる方は読んでほしい。定価4950円ですが……お願いします。
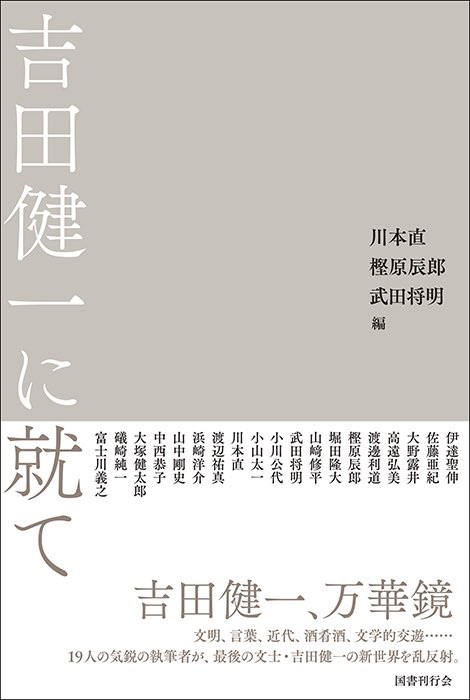
なぜ、自分のような若輩者が泣く子も黙る伝説の出版社・国書刊行会(さまざまな逸話のある出版社なので興味のある方は調べて欲しい)の企画にぬるっと入り込めたのかは、今も謎のままだ。実際もしかしたら全部嘘企画なのでは……と執筆中に何度も思った。なにせ、自分が過去に書いた書籍の執筆仕事は、『百合写真集』(一迅社)に書いた百合ポエムや、『緊縛男子』(一迅社)に載せた緊縛用語の説明文くらいのもので、名のある文士・文学者の方々にお見せできるような仕事は何一つしていなかったからだ(※決して一迅社の仕事を貶めているわけではない、場違いという意味だ)。
きっかけは、学生時代からお世話になっている先輩ライターの方からの推薦と、今回の本全体の取りまとめ役であった川本直さんからのお声がけだった。なぜか川本さんが自分のVTuber関連の記事を読んでくださっていた(??)ことで話が進み、執筆の末席に加わることとなった。
吉田健一という作家に、特段の縁があったわけでもなければ、著書を愛読していたわけでもない。文学史の授業で名前を見た程度。三島由紀夫と喧嘩したとかしないとか、そういう話があったらしいと聞いた覚えがあったような……。そんなスタートからだった。
準備前、色々と話し合いの場が持たれ、吉田健一が無類の酒好きであったことと、僕が夜の酒場で働いていたこととが繋がって、「酒」をテーマに一筆書いてみよう、まぁ、ゆりいかさんなら何とかなるよ、という感じのやりとりだったと記憶している。
そこから約2年ほど「吉田健一の本だけを読む」という日々が始まった。何を書くにしても、ひとまず吉田健一という作家の仕事ぶりを知らなくてはならない。川本さんから渡された必読課題図書リストに掲載の本を購入し、復刊してない本を古本屋で探し回り、昼の編集の仕事、夜のバーテンの仕事の合間合間に、吉田健一だけを黙々と読む。当時はまだ具体的な出版スケジュールも、著書の参加陣も、タイトルも何も決まっていなかった。正直、本当に出るのかどうかも疑わしく思っていた。ただ、文学の仕事の席では、皆が平気で5年とか10年とかの単位で仕事の話をしているのを耳にしていたので、「そういう世界なんだな」と思うしかなかった。
加えて、自分に重くのし掛かっていたのは、(立場上、当然ではあるのだが)著書の実力が足りているのかを見るための査読(早めの初稿提出)があるという話だった。これで、自分の実力が編集担当の方々の目に入らなければ、調べたものも書いたものも無駄になる。
しんどいが仕方ない。ダメで元々なのだし、やるしか無い。そうやって奮い立たせるしかなかった。もしかすると、師匠の元で修行を重ねて初の高座に上がる落語家も、日々こういうプレッシャーの中にあるのかもしれないなと感じて、YouTubeで若手落語家ばかり観る時期もあった。
とはいえ、調べていくうちに、吉田健一の考え方や生き方のスタイルに興味を持てるところが多くあり、読むこと自体が苦になることは無かった。……いや、ちょっと嘘入ったかもしれない。昼の仕事が超絶忙しいときに読んだ『時間』は、何一つ頭に内容が入ってこなくて、本当に悩んだ。途中から、心を静かに研ぎ澄ます時間の余裕がそもそも無ければ、『時間』は読めないなと気づき、河川敷や喫茶店、旅館など、極端に仕事のことを忘れられる環境で集中して読んだことを覚えている。
半年間、ある程度読書を重ねて、それでも書くことには悩んだ。そもそも、批評家でもなければ研究者でもない自分に、独自の斬新な視点で吉田健一を読み込む? 不可能だろう。それができていれば、俺はとっくの昔に作家や批評家になれている。では、書けることはなんだ。自分の視点とは? 他の人には書けないこととは?
色々思案した挙句、行き着いたのは「ライターとして書く」ことだった。とにかく、自分のテーマは酒。ならば、飲むしかないだろう。足を運ぶしかないだろう。飲食店の取材であれば、得意ではないが、慣れてはいる。吉田健一の行きつけの酒場を巡り、過去と現在を比較していけば、何か見えてくるはずだ。少なくとも、そこにしかない情報はきっと落ちてるはずだ。だから、これまでのようにライターとして、取材することにしたのだ。
休日を使って色々巡った。具体的に、どんな店に行き、そこでどんな出会いがあったのかについては、本書を読んで欲しいが、1番の遠出は金沢だった。もちろん全て自費、自腹である。最も高い店で一食3万円したと言えば、この仕事の大変さを想像してもらえると思う(当然、充分に良い思いもした訳ではあるが)。そうやって、直接ゆかりの地を歩き回り、本を読み、人と話して考える。それをグルグルと繰り返して、ワードにメモを書き溜めていく。
執筆の終盤は、仕事で憔悴しきって一筆も書けなかったので、妻に温泉宿に連れて行ってもらい、人生初のカンヅメを体験した。その割にめちゃくちゃ捗ったわけではなく、書けないことに焦って尚疲弊した。こうやって過去の文豪たちは追い詰められていったんだなと追体験できたこと自体は良かったかもしれない。
分量は、たった1万5000字ほど。普段の仕事で1日のうちに編集したり書いたりしている量とほぼ同じである。ベテラン作家であれば、取るに足らない量の仕事と思うかもしれない。だが、本当に難しかった。本の先にいる読者の顔がまるで思い浮かばず、何をどう書けば満足してくれるのか、まるで分からない。
原稿を提出した日の夜。公園のベンチに座って、ちょっと泣いた。執筆できた安堵よりも、「俺は全然ダメだったかもしれない」という敗北感的なもので、どうせ査読で落ちるな……という不安に押しつぶされそうだった。夜道をトボトボ散歩して帰ったら「そのまま失踪するんじゃないかと思った」と妻に言われた記憶がある。
幸いなことに、川本さんから先駆けてOKをもらい、編集者の方からも、内容面で大きな指摘をされることはなく、無事掲載されることとなった。もう一つ嬉しかったのは、取材した各飲食店の写真掲載の許諾を求めた際、数軒から「詳しく書いていただき、ありがとうございます」というお礼の返事をもらったことだ。飲食系のライティングをやっていても、そういう言葉をもらうことは稀だったので、非常にありがたいものだった。
結局「とても苦労しました」くらいしか伝わらないかもしれないが、自分は自分なりのアプローチで文学のフィールドで仕事をできたことが嬉しかったのだ。10代の頃に憧れた小説家や批評家にはなれない人生ではあったが、こういうよく分からないルートを辿って仕事できることもあるんだ。なら、勝負の仕方は色々あるもんだなと、そういう納得の仕方ができたことが、大きかったように思う。これまで三流ながらもライターをやってきたことは無駄にはならないな、と。
吉田健一という作家から、どういう気づきや学びを得たのかについては、また別の機会に書こうと思う。今はとにかく酒が飲みたい。せっかくなら「黒帯」をあけて、乾杯しようか。